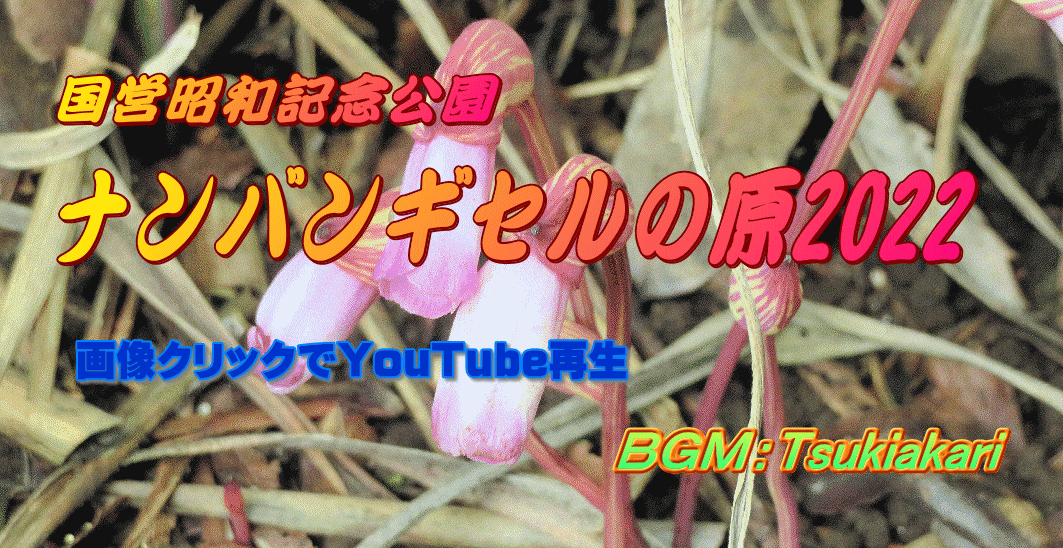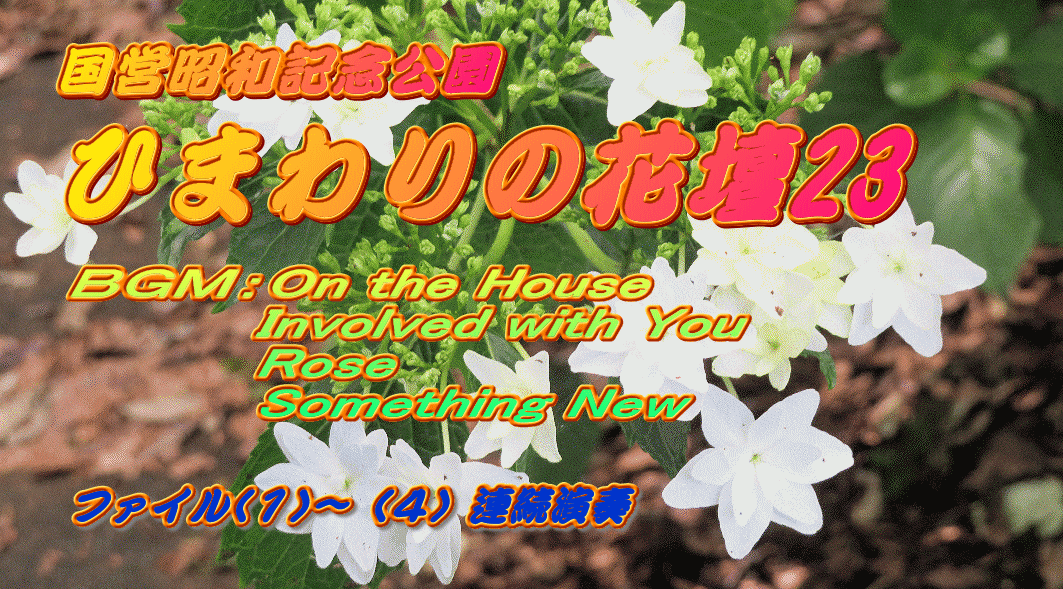

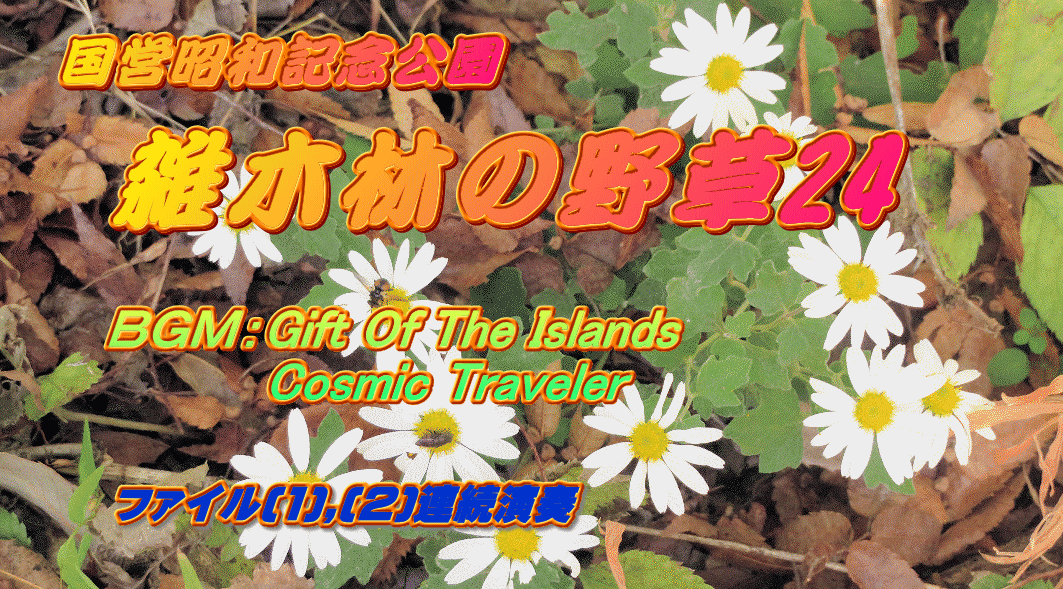
ウインターリリー・ヤマユリ
百合の花は本来は夏の花である。しかし、ウインターリリーは冬の花として提供された。園芸品種として交配して作られ提供されている百合の花は大きく分けて、オリエンタル系とスカシユリ系の2系統がある。

ウインターリリーはスカシユリ系の花であり、夏に西立川口で咲くカサブランカはオリエンタル系の花である。公園では、夏にヤマユリやラッパ状に反って咲くテッポウユリも見ることができる。
ヤマユリで代表される百合の花は、北半球の温帯地域に5月下旬から6月上旬にかけて開花するスカシユリ系の花である。(右の写真)
百合の花は、多年草で草丈50cm~200cm、花の色は、白、赤、ピンク、オレンジ、黄などの種類がある。
百合の花の一般的な花言葉は「純粋」「無垢」「威厳」「自尊心」などと言われている。
公園で咲くウインターリリーは6月頃に咲くスカシユリを利用して耐寒性を強めた品種だと言われている。この冬に初めて展示されるようになった。
次の図は、西立川口に咲くスカシユリと最近提供された3色のウインターリリーを掲載した。
トップページに公開した「公園百合の花23」で現れる百合の花は、この公園で夏期に咲く主な花の百合の種類と新たに開発された冬に咲くウインターリリーを掲載したものである。
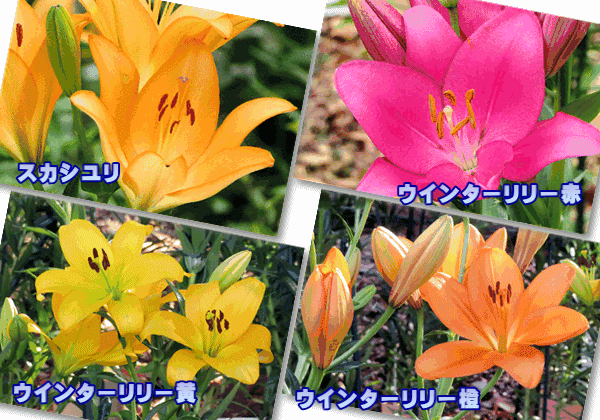

ロウバイ・ソシンロウバイ

ロウバイは落葉広葉樹の低木で、高さは2~5m程度で、樹皮は淡灰褐色で皮目は縦に並び、生長とともに浅く割れる。花期は1~2月で、早生種は12月頃に咲く。花色は外側が淡黄色、内側は暗紫色である。葉の長さは10~20cmの細い超楕円形である。種子は有毒であるが、花やつぼみから抽出された臘梅油はやけどの薬に用いられる。
原産地は中国で、17世紀の初めに来日した。庭木として植えられている。品種には、ソシンロウバイ、満月ロウバイ、白花ロウバイ、唐ロウバイなどがある。ロウバイの基本種は花の中心部は暗紫色で、周囲が黄色であるが、ソシンロウバイは花全体が黄色である。
ロウバイの花言葉は、「ゆかしさ」「慈しみ」「先見」「先導」などがある。
ボケ・カンボケ

ボケは原産地は中国で、日本には平安時代に渡来し、本州から四国、九州で観賞用に栽培されている帰化植物である。名称の由来は果実が瓜に似ていることから木になる瓜で木瓜(もくか)と呼ばれたものが「ぼけ」に転訛したと言われている。
早春から梅に似た花を咲かせて春の訪れを知らせてくれる落葉の低木で樹高は1~2m程度で、株立ちになり茎はよく枝分かれして若枝には褐色の毛、古くなると灰黒色になる。樹皮は灰色や灰褐色で、小枝は刺になっている。花は3~4月に朱色の5弁花を咲かせる。秋には楕円形の果実を結実する。花色は淡紅、白と紅の斑、緋紅、白などがある。冬咲きのカンボケは11月から12月に花を咲かせる。
ボケの花言葉は、「先駆者」「妖星の輝き」「指導者」「熱情」「平凡」「退屈」などがある。
シラヤマギク

サラシナショウマとイヌショウマ
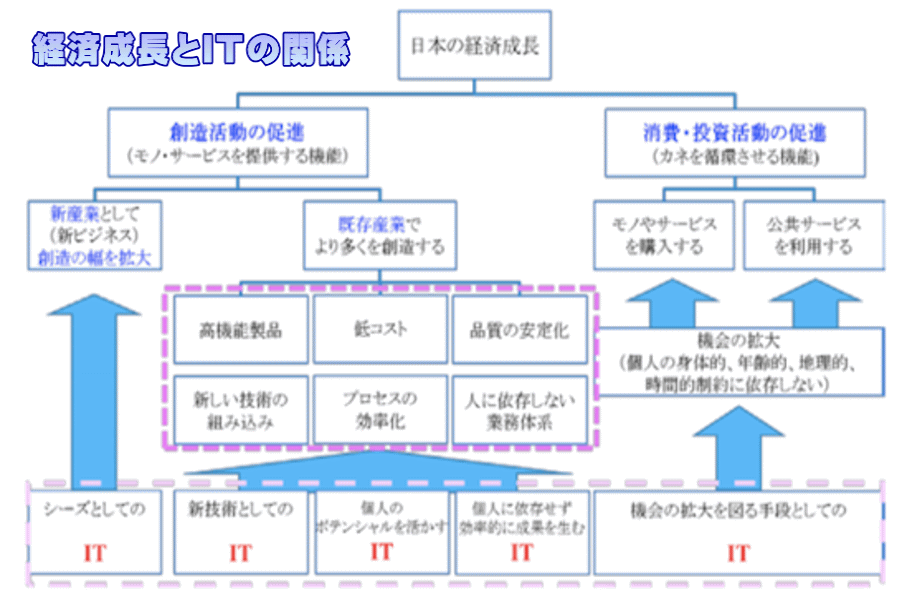
シュウメイギク
シュウメイギク(秋明菊)は、キンポウゲ科アネモネ属の多年草で、秋に美しい花を咲かせることからその名がついている。以下に特徴をまとめる。
________________________________________
🌸 基本情報
• 学名:Anemone hupehensis(または Anemone japonica とされることもある)
• 和名:シュウメイギク(秋明菊)
• 英名:Japanese Anemone
• 原産地:中国が原産だが、日本には古くからあり、京都などでよく見られるため「日本原産」とも言われることがある。
________________________________________
🌿 特徴
• 開花時期:主に9月〜11月(秋)
• 花色:白、ピンク、赤紫など
• 草丈:60〜100cmほど
• 葉:深く切れ込みのある濃緑色の葉
• 花の形:一重または八重咲きで、キクに似た形をしているが、実際はキンポウゲ科である。
________________________________________
🌱 育て方のポイント
• 日当たり:半日陰〜日向が理想
• 土壌:水はけの良い肥沃な土
• 耐寒性:比較的強い
• 繁殖:地下茎で増えるため、放っておくと群生する。
________________________________________
🌼 その他の魅力
• 秋の庭を彩る貴重な花として人気がある。
• 和風庭園にも洋風ガーデンにも合う、上品で風情のある花である。
• 切り花としても長持ちし、茶花としても使われる。
次の図はコパイロットが描いたシュウメイギクのイラストである。
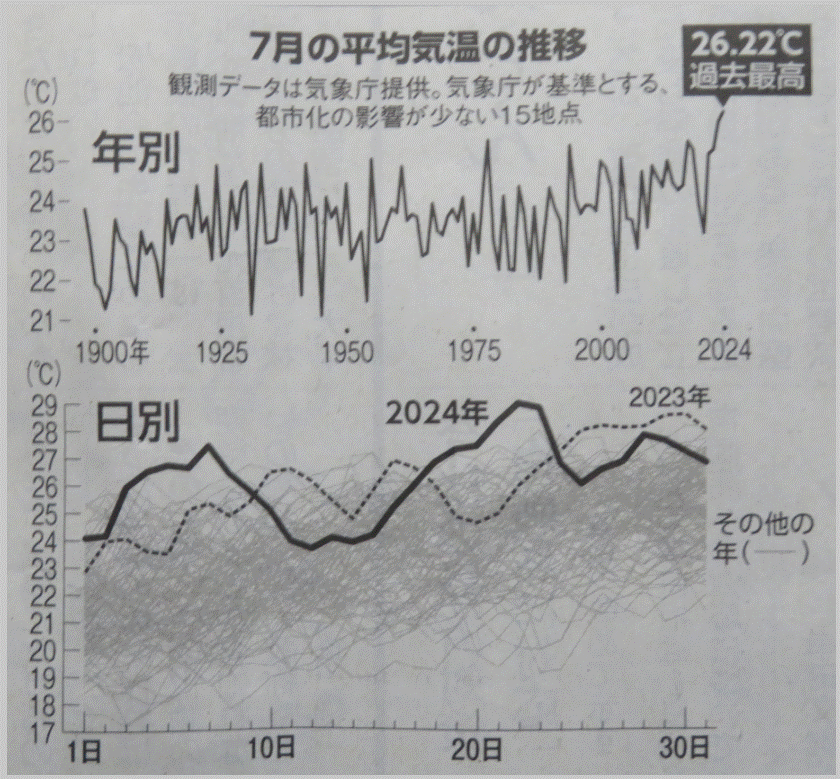
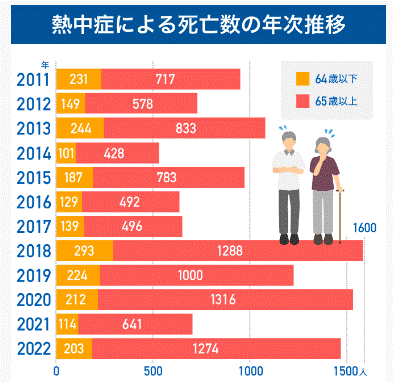
クリスマスローズ
クリスマスローズは冬の寒い時期に咲くバラに似た花でバラとは全く異なる種類の花であり、冬の女王とも言われている。赤、ピンク、白、黄色、緑、紫、黒などの華やかな色の花を1月~4月頃に咲かせる。草丈は30~60cm程度で、花言葉はいたわり、追憶、慰めなどがある。

クリスマスローズは、無茎種といって、茎がなく、根茎から葉柄と花柄が別々に伸びる。多年草で多くは常緑であるが、落葉するものもある。花色、花形のバリエーションが多く、種で増やしている株では、1株ごとに異なる花を咲かせる楽しみのある草花である。
ニゲル種とハイブリッド種の2系統があり、ニゲル種は、開花時期が冬咲きで、12月から2月で、白から咲き進み淡いピンクとなり、やや上向きに開花する。クリスマスローズの名前の由来となった原種である。ハイブリッド種は、春咲きで2月から3月で、花色は白、緑、ピンク、茶など豊富で、うつむいたように下向きに開花する。様々な交配を得て生み出された園芸種である。
クリスマスローズはイエス・キリストの誕生に関わる花で、12月25日の誕生花になっている。貧しい羊飼いの少女マデロンの有名な伝説がある。貧しい少女マデロンが誕生日の贈り物ができない悲しみから流した涙が落ちた土の中から白いクリスマスローズが咲き乱れ、その白い花束を贈り物として聖母マリアと幼子キリストに捧げたという話である。




花木園梅の花分布図



ナンバンギセル
ナンバンギセルはイネ科の単葉植物であるイネ、ススキ、サトウキビ、ミョウガなどの根に寄生し、葉緑素がなく、宿主の根から吸収した栄養分に依存して生育する。全長は15~50cm、葉は被卵形、赤紫色の花を1個つける一年草で、花期は7~9月である。
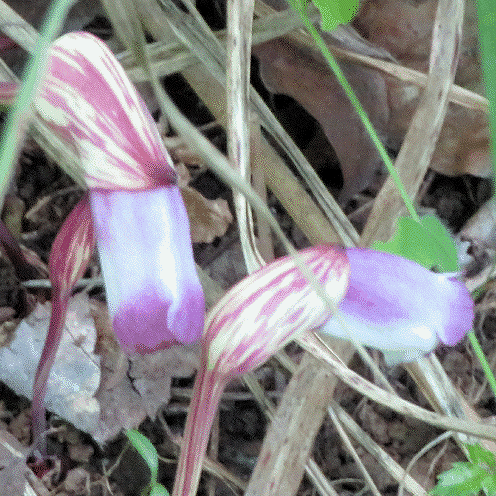
日本を含むアジア東部、アジア南部の温帯から熱帯にかけて生育する。原産地は日本、中国である。日本では北海道から沖縄まで広く分布している。
植物でありながら葉緑素を持たないため、光合成で自ら栄養分を生み出せない植物である。ススキの根などに根元を巻き付けるようにして、自らのからだを食い込ませ栄養分を吸収する。地表に出ている部分は花柄と花の本体だけで殆ど地中に埋没している。宿主の成長は阻害されて、死に至ることもある。
名前の由来は花の姿が南蛮人が使っているキセルに似ていることから名付けられている。花言葉は「物思い」で、うつむいて咲く花の姿を物思いにふけっている姿に見立てたことに由来している。古くは万葉集にも歌われている風情のある花であり、当時から尾花(ススキ)に寄り添って咲く花として知られていた。