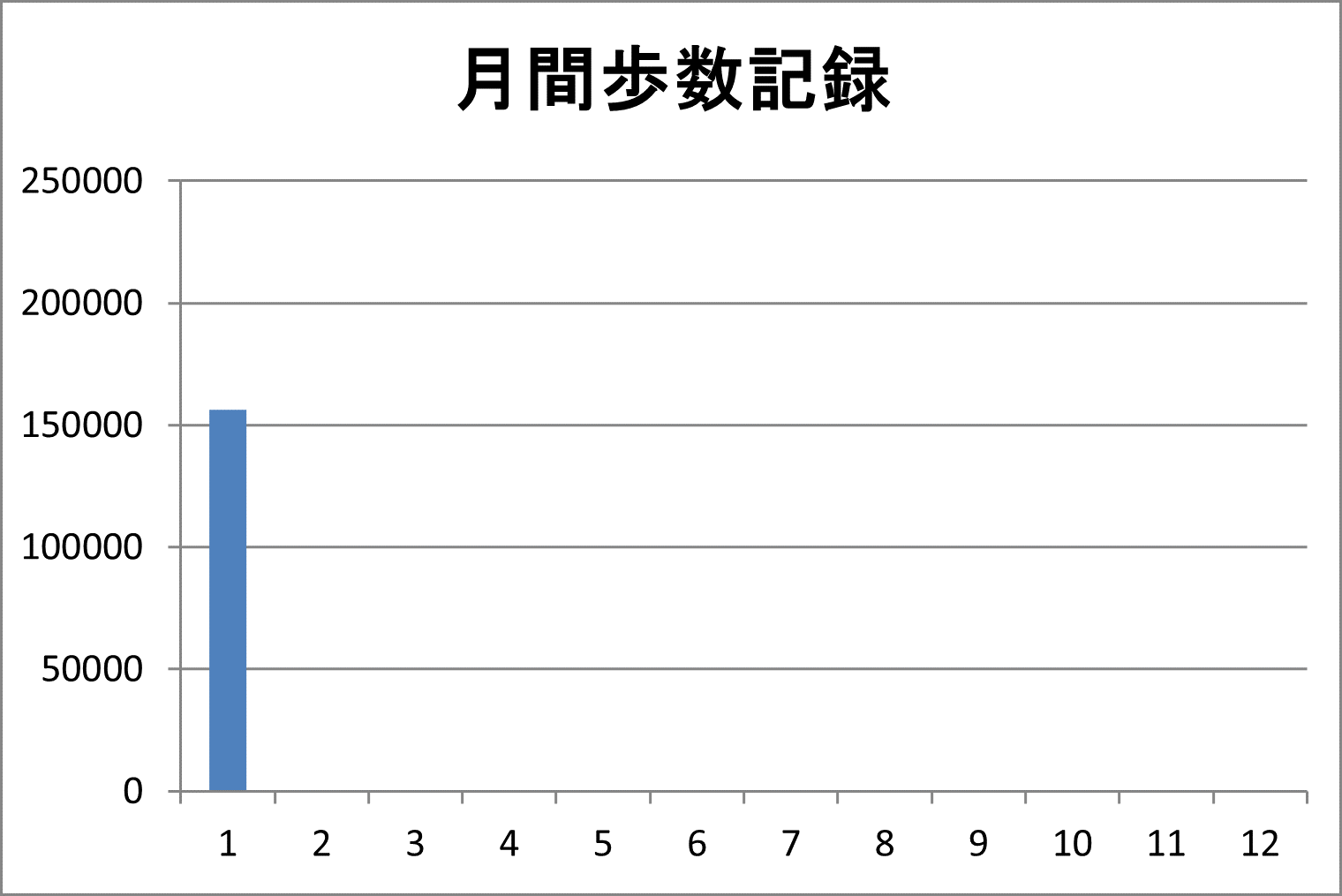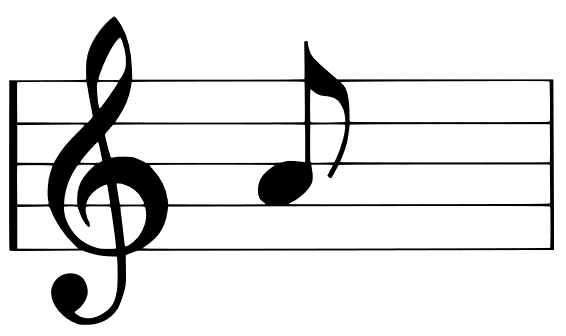1.健康増進のための散策について(音声解説)
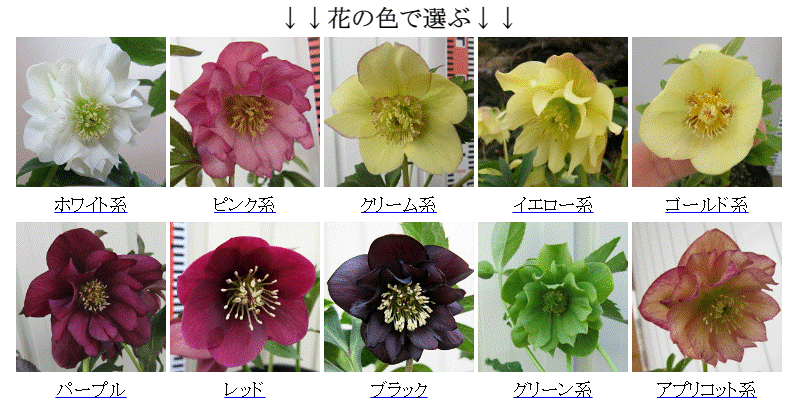
散策は、健康を増進し、日々の生活を明るく楽しいものにする。
子や孫にも迷惑かけず、高齢化社会における健康維持や認知症の予防、高齢者介護に必要な社会福祉費の合理化にも役立つ。
高齢化社会では、健康増進のための散策の奨励とそのための環境整備が必要だ。
高齢者は「歩けば体が軽くなり、生活が楽しくなる」という信念をもち、自らの健康増進のために自ら研究する意欲を持ち行動しなければならない。

公園内の植物や動物に関心を持ち、探求する精神を養えば、老齢者といえども、知の錬磨につながり、認知症の予防にも役立つ。「共生の原理」、「再生の原理」に関心を持ち、自然界の基本現象を把握し、理解し、人間社会に適用する仕組みの創造に結びつけると、人間社会の構造改革をも進展させることができ、価値ある社会の創造が可能になる。更に、ハイテクを橋渡しに、人間社会の一層の成長を図ると、高齢化社会の問題である「老後の安心」にも結びつけることが可能になる。結果、高齢者も含めて豊かな社会のエンジョイが可能になる。
自ら進んで行う散策は最も経済的な活動である。
最近の世の中は行動するたびに多額のコストがかかる仕組みになっている。人もそれに慣れてコストをかけないと行動ができないと考えるようになってしまった。最小の入力で最大の効果を得るのが経済活動の基本原則である。自分の体内に蓄積されているエネルギー源を活用できれば経済的に行動が可能になる。
日本では、経済再生と社会の構造改革を併行して推進する行動が必要だが、今年始めても、少なくとも今後3~5年の歳月をかけて進むことになるだろう。将来の日本社会を考えると、ここでも着実に高齢者も参画して推進する必要がある。そのためにも健康でなければならない。
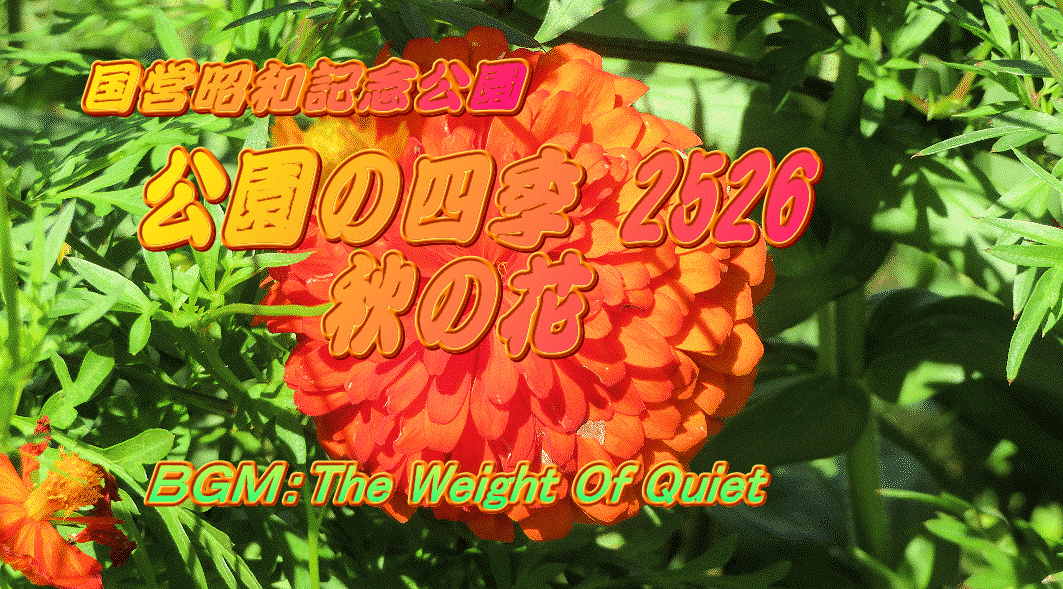
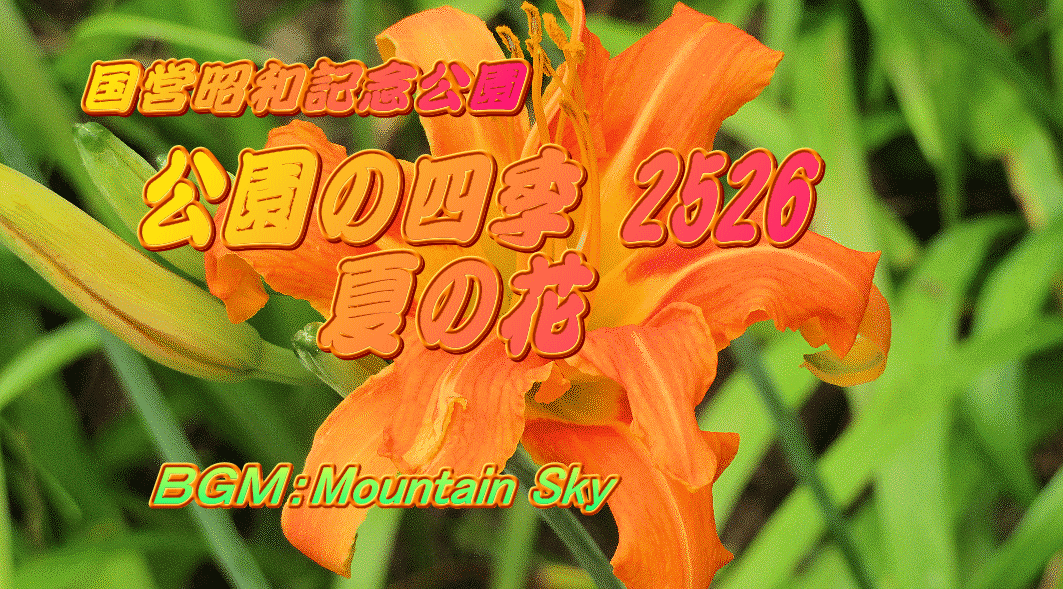

1.公園にも地球温暖化の影響か

現役の仕事を引退して、ネット中心に種々の情報発信を始めて以来10年を超える歳月を経過した。情報発信のネタを公園の草花や木々、水鳥、鳥類、昆虫などの生き物の生態系に焦点を合わせ、写真撮影や観察、関連データ収集、整理、ネットへの情報発信などを行ってきた。最近、この10数年間に公園の生態系が刻々変化してきているのを感じるようになった。
地球温暖化の影響を受けて、気象条件が大きく変化してきている状況は、日本列島での自然災害や海外での山林火災、アジア諸国での水害などのニュースから察知していたが、それらの地球上の環境変化の影響を受けた現象に酷似した現象が公園の中の限られた環境でも発生していたようである。5,6年前までは水鳥の池には冬になると各種の渡り鳥が飛来し賑わっていたが、最近は飛来する鳥の種類も数も大幅に減少した。以前、毎冬に姿を見せていたアオサギも見られなくなった。林の中で観察できたキジバトもいなくなった。庭園の池で飛んでいたトンボや蝶トンボの姿、トンボの2連結や3連結の状態なども見られなくなり、トンボ取りの名人技を見せてくれたカイツブリも産卵しなくなった。
ここでも、地球温暖化の影響が現れ始めているのだろう。注意が必要である。今後の公園の環境変化、日本の環境変化、世界の環境変化、地球上の環境変化により多くの注意が必要となる。
我々の周辺の変化は、「人類滅亡という事件」が発生する方向に動き始めている。
2.庶民の原動力結集で改革推進(音声解説)
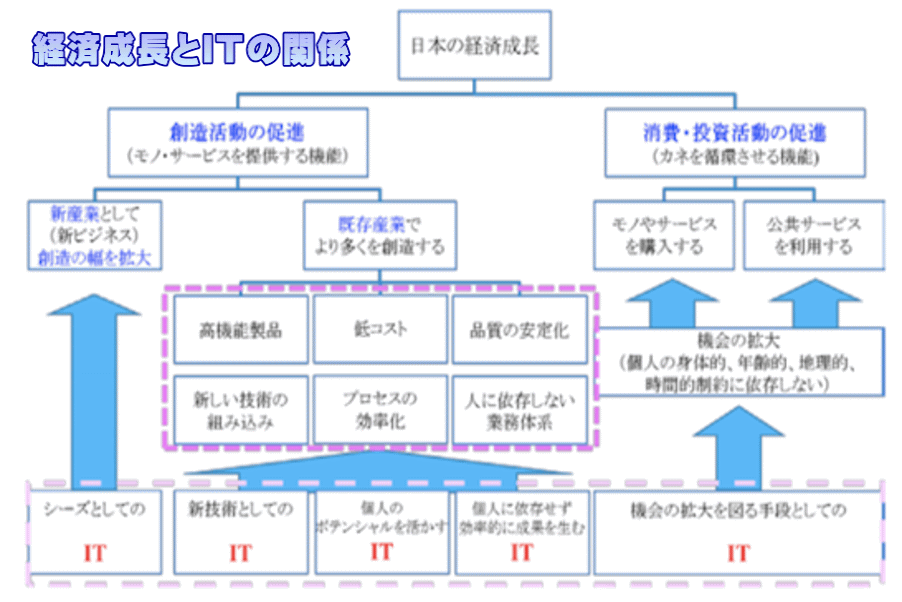
今までの日本社会では、「政治とかね」の問題と言うような政治的問題に対しては、「見ざる、聞かざる、言わざる」と言った無関心な態度を示すのが一般的であった。庶民にとっては、「無関心さ」を示す行動が利口な行動とされていた。しかし、社会が現在のように劣化してくると、劣化の影響受けて損をするのは一般庶民の「無関心」でいた人達である。
無能になった指導者が吹く笛の音色で庶民が無関心のまま踊るようになると、社会はどんどん劣化していき、格差がどんどん広がり、最も損をする人は無関心でいた人達となる。このような状態が30年以上も続いたのが平成時代であった。平成時代に日本国内の格差は広がり、庶民は貧しくなっていった。なかでも、科学技術や各種産業の主要分野で、世界的に比べてレベルの低い国になってしまった。それにつれて、庶民の日常生活も苦しい人達が増えた。GDPもドイツに抜かれて世界4位に落ちてしまった。このままでは、やがて、インドに抜かれることになり、その後もどんどん堕落することになるだろう。同時に、庶民はどんどん貧しくなる。このままではレベルの低下は今後もどんどん続いていくことになる。国家が破滅するようなことになると、多くの国民は極貧生活に追い込まれることになる。そこで、「国としてのレベルの低下を防ぎ、世界的なレベルを高めることが重要な政治課題」となる。そのための工夫と努力が必要となり、そのための行動が不可欠な政治課題となる。
政治は、庶民の一票から始まり、庶民の総意で社会や国の進む方向を決め、行動の仕方を取り決め、庶民が一体となって全員で行動し実現させるものである。戦後の日本経済の成長や庶民の豊かさの確保はそのような行動の集まりの結果生まれたものであった。だから、すべての国民が揃って豊かになることができた。民主主義の原則を守り、民主主義的に行動した結果である。
現在の日本社会のように選ばれた上級国民の能力が喪失し社会が堕落すれば、戦後のように庶民一人一人が責任を持って行動することによって新しい時代に向けた社会改革が可能になる。庶民が無関心を捨てて積極的行動に変化することで可能になる。社会問題や政治問題に対して大いに関心を持って、庶民自らが頭を使って、他人の話や世間の人々の意見を聞き、他人と話し合って自分達の考えをまとめ、自分達の考えを主張し行動することが重要である。政治家を頼りにしすぎたり、何も注文せずに単純に任せたりするようになると成果は得られなくなる。
民主主義社会では、庶民一人一人が社会の一員となって行動することによって庶民全員で社会の成果を上げ、庶民一人一人がその成果の恩恵を受けて全員が豊かになっていくことができる。その行動をまとめていく人がリーダーである。たとえ、相手が「首相」という位置にいる人であっても、その相手に考え方や行動を全て任せてしまうと、社会的な成果は期待できなくなり、庶民はその成果の恩恵を受けられなくなる。
民主主義社会ではこのような考えに基づく行動が必要になる。このような行動を適切に指導できる人物が、成果を庶民にもたらせる素晴らしい指導者となれる。そのような役割を国のレベルで推進できるのが民主社会での「首相の役割」になる。
選挙時には不合理な人を政界から排除する行動も必要となる。法治国家で不適切な発言や行動を行う政治家に異議を唱える。民主主義的な成果が期待できない言動や行動に対して異議を唱えることも必要である。
異議を唱える場合、個人のレベルで弱ければ、グループや集団の力、組織の力にまとめ上げて実行する。それを庶民が力を合わせて推進する。それが民主主義的行動である。そのための手段はネット上にたくさんある。みんなのスマートフォンの中にもある。
一人でも多くの人が積極的に、このような行動に参加し実行できるようになると、社会を変えることが可能になる。明治維新のように戊辰戦争や社会騒動に頼らなくても、庶民が社会やネットを利用して時間をかけて根気よく活動すれば、平和な状態で社会改革を推進し達成することが可能となる。それが日本人であり、日本社会である。その先には夢が持てる社会が現れる。
庶民の関心と庶民の声で、「もの申す庶民の集まり」が社会を変えていく原動力になれるのだ。その原動力を中心に、質のよい優秀な経営者や社会の指導者、政治家、その他の社会改革に必要な人々が集まるようになる。そのような人達が一丸となって推進する「かたまり」が、新しい日本社会を改革できる集団として生まれ、改革を推進できるようになる。庶民の原動力がその「かたまり」を育てることになり、庶民の原動力で優秀な人材を結集させることが重要となる。
この行動が日本の民主主義であり、議会制民主主義の基本である。
3.価値ある社会の創造(音声解説)

最近、テレビでもYouTubeでも「103万円の壁」の話題で賑わっている。国民民主党の街頭演説では、日本の国の将来がバラ色に変わるかのように語られている。本当だろうか。
1995年頃、平成時代の初期に設定された「壁」が30年間も検討されずに放置されていたことが問題である。その間に世界情勢も世界経済も大きく変化し、欧米の先進国の多くはこれらの問題に適切に対応できたのに、日本は長期間、適切に対応できなかった。これは日本の政治家や社会の指導層,財務省関係者、経済関係者、官僚、その他の一般国民などの怠慢に起因している。その影響を受けて、日本社会は大幅に劣化し、経済成長は停滞し、庶民の生活水準も衰退した。庶民の給料も伸びず、多くの人が貧しくなった。世界の比較経済の中で日本は貧乏くじを引かされてしまった。
令和になって、感染症コロナが世界で発症し、日本社会にも短時間に感染が広がった。それらへの対応能力の弱さを国民が実感するにつれて、経済的にも弱体化した日本社会の実力の低下レベルを人々は感じるようになった。現在、議論されている「103万円の壁」問題も、財政や財務省、税制と関連付けられた一面からの問題点が対象になって議論されているが、平成時代にこれらの問題に影響を与えた日本社会の劣化と関連する問題を組み入れて考えると、それ以外のたくさんの要因が関係していることがわかり、全体に及ぼす影響はその他のもの方が多いとも言える。その環境下で、日本の国は自分たちの力で富を得る能力を大幅に低下させ、お金を流通させることでなんとか生計を立てていたが、入るものが減少することで減耗が目立つようになり貧しさを感じるようになった。企業や一部の富裕層は、内部留保や蓄財を利用して自己対策を講じたが、一般庶民にはそのための対策を講じる余裕がなかった。
103万円の壁問題も、国の経済成長や産業政策の失敗が原因で発生した問題であるが、目先の金儲けにこだわり、金さえあれば何とかなるという安易な考えが先行し、国の基本的な問題である科学・技術への関心や産業への対応策の検討を怠った結果発生した問題である。なかでも情報分野との関係で基本的な考え方で誤りを犯した罪は大きい。すべては、政治家や社会指導層の責任である。
国民民主党の話題では、103万円の壁問題が金星を挙げたかのように言われているが、本来は日常的に検討されるべき課題であり、30年もの期間、放置されていたことが問題である。与野党の政治家達は責任を感じて、まず、国民に謝罪すべきをそれも行わずに、手柄だけを誇張する態度は許されるべきことではない。それを参議院選を有利に導くために利用する行動は許されない。無責任な政党だ。
この問題は、多くの一般人が個人で確定申告を行わない日本社会の慣習が齎した問題かも知れない。個人申告を行えば、可処分所得や納税額などを常に意識し、現法内で対策可能な節税手段などを検討している筈だ。今後、正業、副業の兼業が可能になってくると、時間の効率的な活用や教育・訓練対策の実施なども含めて、これらの問題との関係も日常的に無視できない課題になってくる。税法上の法律や仕組みの問題の検討は政治家や官僚の仕事であり、常に正常な状態に維持する役割を持っている。
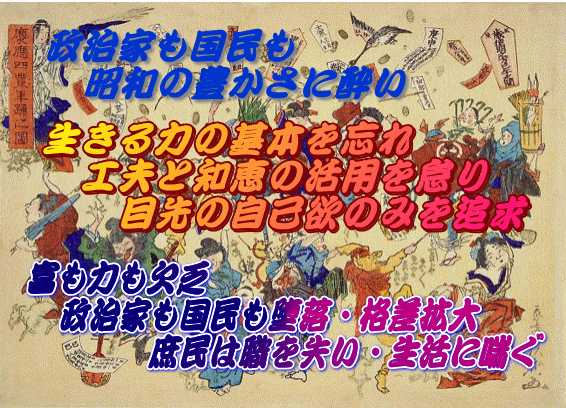
103万円の壁に関する問題を財務省の体質問題に限定して議論する場合でも、この種の問題を解決すれば日本経済や社会的体質が好転し、庶民の生活が直ちに向上し始めるかのごとく語られていることは正しいとは言えない。日本社会の構造的な体質問題はもっと根深いものであり、広い観点から議論されるべき問題である。平成の30年間に悪化した社会や経済、産業の諸問題は財政問題への対策だけでは解決しない問題である。
税務処理の金銭的問題に限定して考えても、検討される処理内容が具体的に実践されるのは26年度以降の確定申告からとなり、その間の2~3年の間は庶民の物価対策は現在のやり繰りでの対応のみになる。このレベルでの対策では、急速な物価高の上昇には対応不能であり、賃金上昇と物価の高騰問題が負のスパイラルに突入した状況では、国民民主党の主張するような庶民の生活水準の改善は永遠に効果を示さないことすら生じる。更に、それ以外の人間の体質的な問題点の存在を考えると、3党合意レベルでは効果を期待することは困難である。場合によっては、悪化する可能性がある。
「103万円の壁」レベルの財政処理による対策では、庶民に配られた金銭的ゆとりの供与程度の内容でしかなく、生活余裕のある人には一層有利な条件が与えられるが、持続的経済成長や社会の活性化のための効果的な投資に役立つとは必ずしも成らない。更に、経済活性化のための諸活動の過程で無駄が多発し、事態が悪化していく可能性すらあり、真の問題解決には進まないであろう。
経済活動や産業構造のための環境整備、活動に従事する人々の能力の評価、適正な必要人材数や必要な指導者の確保、技術水準の評価と人材の教育などの根本的な課題が沢山あり、国内環境での働く職場の創造と職場の充実度の向上などの諸問題を十分検討し体制を整備する必要がある。もっと重要な問題として、それらの計画を作成し組織的に実践していく能力や指導者の条件が、日本社会で具備されているかどうかすら問題になってくる。短期間で解決できない課題が沢山ある。
これらの問題は平成30年間に処理されなかった課題であり、昭和時代よりも平成時代に日本社会の能力レベルが低下している一面がある。政治家やその周辺の一部の関係者が考える対策立案では、実現効果を期待できない恐れがあり、具体的な実績・成果が得られない可能性がある。また、納税基準を単純に変更できるようになる問題についても、基準の変更によって安易に富が得られる手段としてその内容が知られるようになると、従来の試行錯誤を繰り返しながら富の不足を逐次補う地味な努力ができなくなってしまう可能性もある。今後、国民民主党が主張している「103万円の壁」政策を適当な期間で変更することを繰り返すことにより、単純なバラマキ効果が財源に関係なく実現できるようになったりする可能性も生じる。その場合、資源の制約から経済成長が停滞するような事態に至ると、逆に損失が増大するようになり、収支のバランスを欠くところまで進むと社会が破壊される結末になる。

世界情勢の変化に伴って、世界の経済環境が大きく変化し、物価の高騰が顕著となり、円安の悪影響を受けやすくなっている日本の経済状態は好ましくない環境に追い込まれている。その結果、庶民の生活にも深刻な打撃が与えられるようになった。同時に働き方改革の推進が進められて、見かけ上の労働人口の減少や労働時間の短縮などが進み、各分野でサービスの量的・質的変化が生じるようになってきている。
これらの社会に存在する根本的な問題を無視して、目先の財政上の問題のみを取り上げて単純に数値を取り入れた成果モデルを作成し絡繰りが展開できても、真の問題解決には至らない。逆に、一定時間が経過した後失敗に気付いても、その段階ではどうすることもできない状態に陥ってしまう可能性がある。応急的対応でない制度的内容に変更を加える場合には、現状分析や関連事項についての検討が不十分なまま、短期間に急いで展開すると、アベノミクスと同様な社会の質的劣化を進めることになり、修正が困難な危険な状態に進んでしまうことになる。
本質的な問題点は社会の根底にあり、日本社会の存在を左右する重大な問題である認識が必要である。安易に少数政党の勢力拡大に利用されたり、参院選対策や当面の生活改善に役立つレベルの中途半端的な対策では平成時代の失敗と同じ失敗を令和時代に繰り返すことになり、社会を一層悪化させる危険性がある。それほどまでに日本社会が劣化してしまっていることを十分に認識することが重要だ。金銭的な対処法では解決できない水準にまで劣化した現状認識が重要である。このまま、進むと投資しても価値を生めない社会になってしまう危険性が大である。「希望の光」をも見失ってしまうことになる。
与野党の枠を超えて、リーダのエゴ、集団のエゴを捨てて、客観的なデータに基づいて多角的に議論して、可視的に進むべき方向を明確にして検討を進めて欲しい。その場合に次の課題を前提に実践して欲しい。
日本社会の最重要課題は、
① 刻々進んでいる「社会価値の低下」を防止して、
② 「投資価値ある社会の実現」「希望の光を求めて」
行動することである。
この行動の向かう方向は 弁証法の「止揚」の概念をそのまま実現していくことであり、その方向と内容を実社会で可視的な一つの形として表現し、その方向に向かって行動を始めることになる。


老人の自覚(音声解説)

最近、自覚できた一つのことは「ネガチブな考え方に陥らないこと」である。
老いれば必ず衰える。当たり前である。若いときに比べれば、老化を意識してネガチブな考え方になりやすい。これも当然のことである。しかし、自分なりの範囲を定義し直し、その範囲内に限定して考えると、ネガチブなものが、ポジチブに考えられるようになる。これは不思議なことだ。
人生で一つでも多くのことを達成したい。じゃ、どうするか。自分の行動範囲を自分で適宜限定しながら、常にポジチブな考え方をとり、それを維持して行動する。少しずつ範囲を広げながら、少しずつ場所を変えながら、行動を続ける。年齢に関係なく、この行為を繰り返す。そこに自分の存在を発見できる。
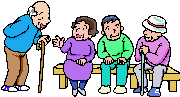
同じ場所に、毎年咲く公園の花の命は、数日から数週間のものが多い。気象条件の変動に合わせて、自分たちが咲き誇れる限られた期間に、それぞれ素晴らしい花を咲かせる。一定の期間が過ぎると瞬く間に、その場所に咲き誇っていなかったように消えていく。油断すると、素晴らしい写真を撮影することもできないことがある。何回か、経験した。
しかし、一年の歳月が過ぎると、同じような場所に同じような美しい花を再び咲かせて生命を謳歌してくれる。いつの間にか、毎年その花をその場所で鑑賞できることが楽しくなってくる。草花はその場所に咲いていない、我々が絶えてしまったと思っている長い期間も、静かに次に咲き誇るための準備を土の中で続けていたと思うと、素晴らしい再生のための行動だと賞賛したくなる。この持続性の努力が人間にも必要だ。
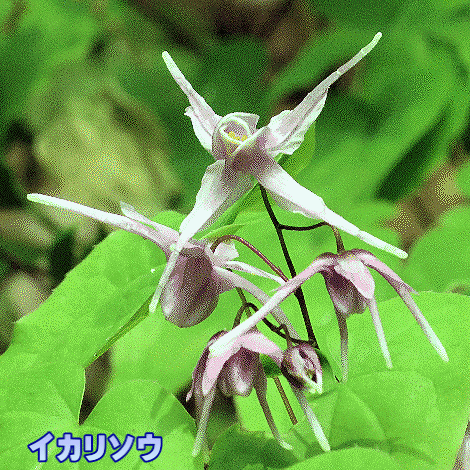
毎日のように公園に通い続けていると、同じ花に何らかの絆を感じるようになる。去年の花と今年の花は「同じ花なのだろか、違った花なのだろうか」気になる。年々、同じ場所に咲く花はその種族の持続性のあらわれなのであろう。小さな花も自然の持続性に貢献しているのだ。素晴らしい。
人の社会でも、高齢者は積極的に社会のリーダ的役割を若者に譲り、一歩下がって、若者に協力して自らの経験を生かして、21世紀にふさわしい社会の改革を若者と共に進めるべきだ。社会基盤の強化が進めば人々は安心して暮らせるようになり、幸せを感じるようになる。そうなれば、日本が再び世界をリードできる国になる。
若い有能なリーダーを中心に、すべての国民が協力できる社会が生まれると、高齢者も「高齢者の支えがあって初めて人間社会は健全な進歩を成し遂げることができる」という自覚を持つことができるようになる。みんなが楽しく幸せを感じることができるようになる。
「高齢者の知恵」と「若者の斬新さと逞しいエネルギー」を活用した社会改革を進めたいものだ。
10年後には、人生110年、120年時代が訪れるだろう。高齢者も時代の変化に遅れないように健康に生きる努力が必要である。
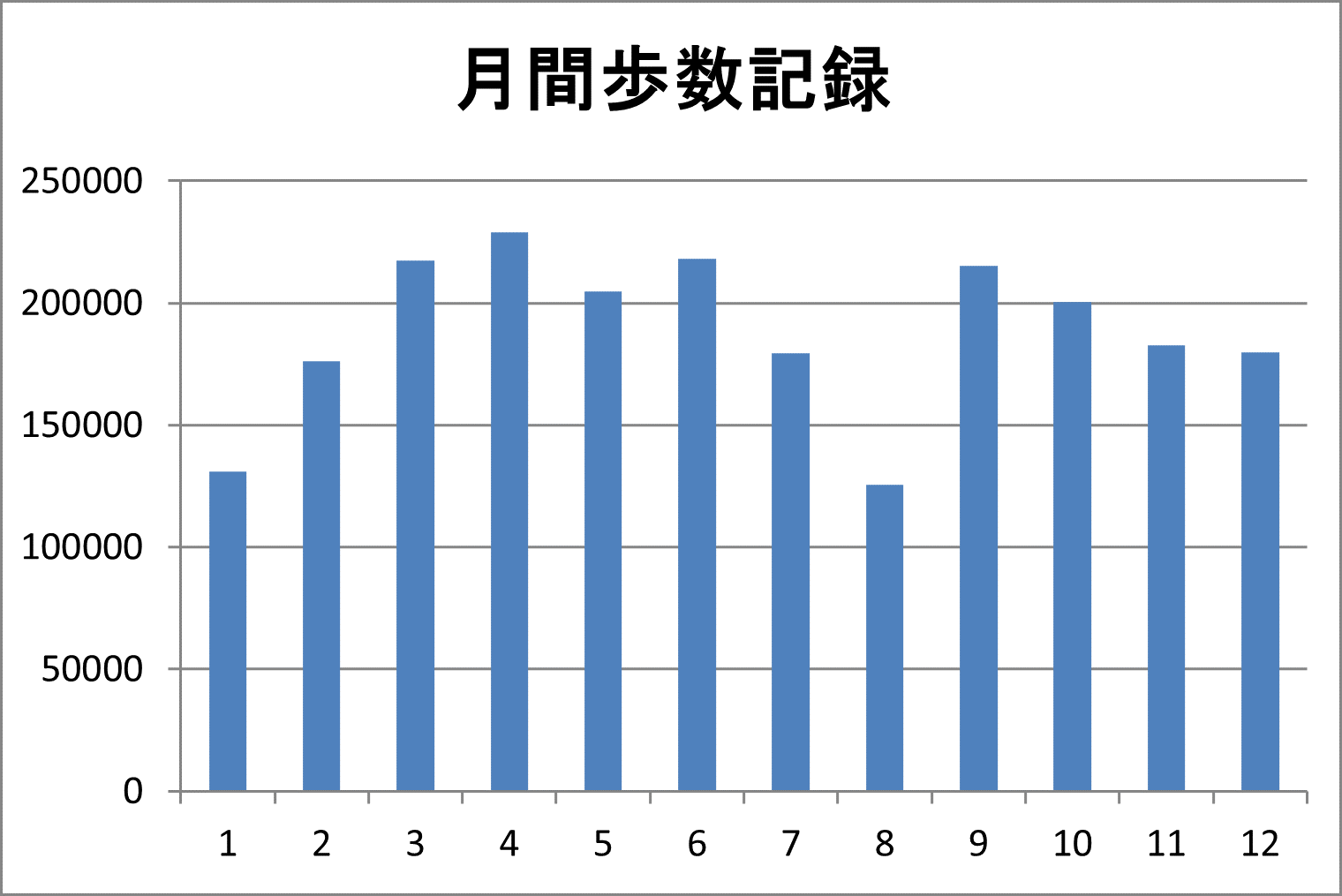
-
月間歩数目標 7万歩以上
月間歩数実績 各月右の図
年間歩数目標 100万歩以上
年間歩数実績 2,259,700歩